

もしもに備える目的でエンディングノートを書くときに重要なポイントがあります。ここを理解してから書かないと効果は期待できないので、まずはそのポイントから理解しましょう。
目次
本当に役に立つエンディングノートを作るための9箇条
①書きにくいからこそ医療と介護のページから書こう

人生の締めくくりに!と意気込むと書いておきたいことが多くなるのは仕方がないことですが、エンディングノートは全部のページを書こうとするとまず書けません。
エンディングノートは書く項目が多いので、全体像を目の当たりにしてこんなにあるんだと引いてしまって、氏名・住所、生年月日あたりで止まってしまう人が多いようです(苦笑)。
多くの場合、エンディングノートが活躍するのは書いた人の緊急時や亡くなった後です。
胃ろうをして良かったのか?しない方が良かったのか?と、亡くなった後まで悩み・葛藤されているご家族を成年後見人として見てきました。もしエンディングノートに胃ろうについてのお母様の希望が書いてあれば、どれだけご家族の救いになっただろうと思いました。

エンディングノートを書くことで、もしものときの家族の負担を少しでも軽くしたいなら負担の大きな項目から書き始めましょう。
もしものときに家族が最も知りたい、かつ本人にしかわからないところからです。
優先順位が高いのは医療や介護のページ、中でも胃ろうをして欲しいのか?など延命治療の希望から書き始めることをおすすめします。
②エンディングノートは本音で書こう
エンディングノートには介護の希望を書くページがあります。
「認知症や寝たきりになった時、介護をお願いしたい人や場所は?」
・自宅で家族に介護をお願いしたい
・自宅で、プロのヘルパーなどに手伝ってもらいながら家族と過ごしたい
・介護施設や病院に入れて欲しい
・家族・親族の判断に任せる
家族に負担をかけたくないと考えて家族・親族の判断に任せるを選びたくなる気持ちはよくわかります。でも本人の希望・気持ちがわからなければ・・・

お父さんは自宅で介護をしてほしいはず

お父さんは施設で過ごしたいはず
と、お父さんはこうして欲しいはずとそれぞれが自分勝手に言い出します。
当たり前のことですが、家族といってもそれぞれ価値観が違うので介護の方針をめぐって家族が揉めてしまうことがあります。さらに遺産分けにまでその影響が及ぶこともあります。
安易に家族・親族の判断に任せるを選ぶと家族が揉める火種になります。

もしものときに家族が知りたいのは、こうして欲しいというあなたの本音です。エンディングノートにはあなたの本音を書いてください!
エンディングノートを書いておくよりも本音を直接伝えておいた方がよいのは当然のことです。
③必要最低限の言葉の意味を理解してから書こう
エンディングノートは、一度書いても気持ちが変われば何度でも内容を書き直すことができます。
ただし、前提となる最低限の知識がないままにエンディングノートを書いているとしたら、それは自分の意思を正しく表したことにはなりません。
例えば、エンディングノートにはリビングウイル、尊厳死などのあまり馴染みのない言葉が沢山出てきます。言葉のイメージだけでなんとなく記入してしまっていませんか?
また、法定後見と任意後見、2つの成年後見制度の違いを理解していますか?
法定後見の申立書に後見人の候補者を書く欄がありますが、必ずしも候補者が後見人に選ばれるわけではないことを知っていますか?
リビングウイル・日本尊厳死協会の会費や入会方法、成年後見制度の概要について簡潔にまとめました。エンディングノートを書き始める前に目を通しておくと安心です。

必要最低限の言葉の意味を理解した上で、エンディングノートを書くことが本当に役に立つエンディングノートを作る最大のポイントかもしれません。
④正確な情報を元に書こう
エンディングノートには正確な情報を書いておくのは当然のことです。資産のページは通帳や証券を手元に準備して書きましょう。そういった資料を準備する過程でほとんど使っていない口座に気づいて、解約を検討するきっかけにもなります。
不動産をいくつもお持ちの方は、納税通知書だけでなく、登記事項証明書や権利証(登記識別情報)を確認しましょう。
自宅ならどんな書き方でも家族には伝わると思いますが、自宅以外の不動産、特に相続した田舎の土地など家族の中で自分しか把握していない不動産は登記事項証明書を見ながら所在や地番を正確に書いておきましょう。
エンディングノートならまだしも、遺言の場合は曖昧な内容を書いてしまうのはトラブルの元です。もれなく不動産を把握する方法はこちらが参考になると思います。
関連|Q. 父名義の畑や山はどうやって調べればいいですか? 【不動産の調査】
⑤個人情報を書きすぎない
エンディングノートの空欄を正確な情報で埋めながら書き進めていくのはなかなか爽快な気分です。
そして、情報がまとまってくると、このエンディングノートを見ればすべてわかるようにしておきたいという欲が沸いてきます。具体的には暗証番号やパスワードもまとめて書いておけば便利だろうと思ってしまうわけです。
ただし、ここで気をつけて欲しいことがあります。

あまりに詳しく書きすぎるとエンディングノートが個人情報の塊になってしまうので危険です。特に資産のページは、家族が口座や不動産の存在を漏れなく把握できる程度の情報にとどめておくのが無難です。
個人情報を詳しく書きすぎないようにしつつも、家族が知らないことを書いておくことは大切なポイントです。
- 借金の保証人になっている
- 前婚で子供がいる etc.
他にも色々あると思いますが、保証人になっているかどうかは自分しか知らないことの代表格かもしれません。
前婚で子供がいることは保証人とは違って、戸籍を確認すればわかることですが、親が亡くなるまでに親が生まれたときから現在までの戸籍を調べたことがある方はどれだけいるでしょうか?
前婚で子供がいるかどうかは、こと相続に関してはとても重要な情報です。前もってわかっているのと知らないのでは相続が開始した後での対応は大きく変わってきます。
直接、話をしておくことができればそれにこしたことはありませんが、伝えにくければエンディングノートに書いておくのも1つの方法でしょう。
⑥遺言の有無や保管場所を書いておこう
エンディングノートに遺産分けの希望を書いたところで「遺言」としての効力はありません。知らなかったという方は、ここでしっかり覚えておきましょう。
効力がないにもかかわらず、「遺言について」というページがエンディングノートにあるのは、遺言を作成しているのかどうか、作成していれば保管場所などを書き留めておくためです。
必要なときにエンディングノートを見つけてもらえるかどうかにも関連することですが、自筆証書遺言は書いていること、その保管場所を家族が把握できるようにしておく必要があります。
また、遺言を書いていない人が多いので「作成していない」にチェックして終わる方がほとんどなのかもしれませんが、それじゃもったいない!
エンディングノートの家族や親族のページを書きながら、まずはこの2点を把握しておきましょう。
- 自分の相続人は誰なのか?
- 自分は誰の相続人になるのか?
これを把握した上で、遺言を作るかどうか?相続人の立場なら遺言を書いてもらっておく必要はないのか?について早めに考えておくことが大切です。
遺言は必ずしも誰もが書いておくことはなく、自分の財産を誰にあげるのかについて自分で確実に決めておきたい人が書いておけばいいと考えています。
とはいっても遺言を書いておかないとトラブルになる可能性が高いケースはあります。
関連|相続事件簿から学ぶ|遺言がないと問題が起こりそうな人はこんな人
⑦見た目や形式にこだわらない
必要なときに書き留めておくノートがあって、結果的にエンディングノートに書いておきたい情報がそこに整理されていくのであれば、それが普通のノートでもまったく問題ありません。
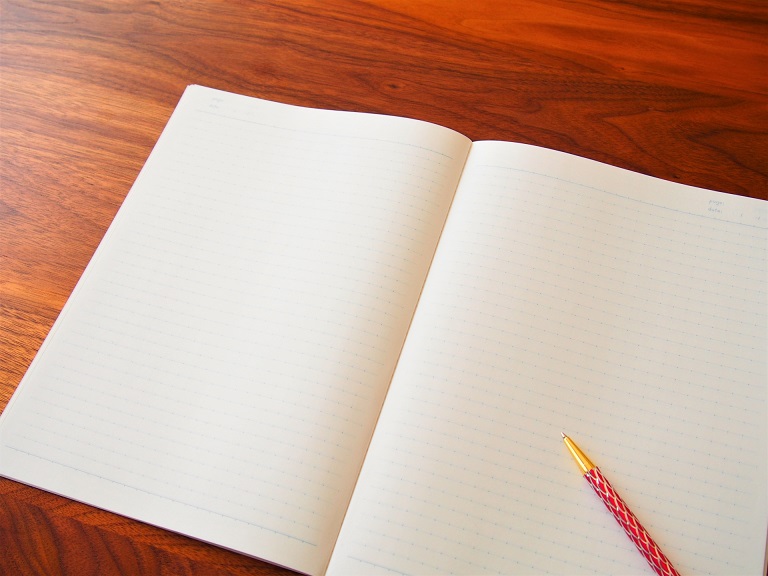
父が祖父母の葬儀の時に書いたというメモを見せてくれたことがありました。
それはメモというレベルではなく、ごく普通のノートに何ページにも渡って葬儀に関することがこまごまと書いてありました。
見た目は100均で売っているような普通のノートでしたが、パラパラと見せてくれた中身は完璧すぎるエンディングノートでした。
祖母が亡くなる前の数日について日記的なことも書いてあって、さすがにそれには気が付かない振りをして返したけど、どんな内容なのかとても気になりました。
もう20年以上前になりますが、正月に祖母が入院していた病院を訪ねて結婚の報告をしたときが僕が祖母に会った最期になりました。
僕にとっては祖母というよりも母代りだったので、祖母の最期について知りたいという気持ちもありましたが、やっぱり見てはいけないと思いました。
見た目や形はいわゆるエンディングノートには程遠いけど、父は父なりに父自身も気が付かないうちにエンディングノートに代わるものを準備している。父の書いたノートを見てそう思いました。

エンディングノートの見た目や形式なんてどうでもいいこと。
大事なのはその中身です。
エンディングノートというネーミングなので当たり前のように紙媒体をイメージしますが、ネットバンキングやSNSがライフラインになっている現在ではノート(紙)だけで完結させるのは無理があるのかもしれません。
エンディングノートは手書きしないといけないと思いこんで、それが書けない理由になっているとしたらもったいないです。必要な時に必要な情報が確認できるならパソコンなどを活用してもまったく問題ありません。
⑧定期的に見直して情報の鮮度を保とう
体調や心境、交友関係など、すべてのことが時間とともに少しずつ変化していくものです。
エンディングノートに限ったことではありませんが、一度書いたところで時間とともに書いた内容はどんどん古くなっていきます。定期的に見直して情報を更新する必要があります。
自宅の防災グッズの点検をしたときに、古くなっていた非常食や防災グッズを買い直しました。

非常食は賞味期限・使用期限が5年というものが多かったですね。毎年、見直すのがベストだとしても忘れてしまって2,3年経ってしまう人が多いのでしょう。
それでも期限が切れてしまわないように、余裕を持たせて5年にしているんだろうと実体験として感じました。
エンディングノートに限らず、理想を言えば1年に1度、誕生日や年末年始に見直すのが良いタイミングだと思います。
最近は出さないという方も増えてきましたが、年賀状のリストなら毎年見直すだろうと思うので、エンディングノートの緊急時の連絡先の見直しを中心に12月に全体を見直すのはいかがでしょう?

エンディングノートも定期的に見直さないと意味がありません。
⑨エンディングノートを書くことはスタートです
エンディングノートを書いておきたいと思っても、ほとんどの人が書いていないのが、エンディングノートの残念な現実です。
だから、もしエンディングノートを書くことができたら、そこで満足するのは本当にもったいないと思います。エンディングノートを書くだけで十分なんてことはほとんどないからです。
亡くなった後の手続きはもちろん、入院や施設の入所手続きなど必要なときには自分ではできないこともありますが、葬儀やお墓の準備は前もって契約しておけるので自分の思い通りに準備しておくことができます。
考え方次第ではエンディングノートに書いておくよりも自分でやってしまう方が早いし確実です。

書き終えることがエンディングノートのゴールではありません。書いておきたいほど気になっていることを実現するために、エンディングノートを書くことをきっかけにして行動を起こしましょう。
エンディングノートを書くことはスタートです。
この9箇条は本当に役に立つのか?

この9箇条の内容ならきっと役に立つだろうと自負していましたが、実際の事例で検証できていなかったことがずっと引っかかっていました。
僕の活動をいつも応援してくれた義母が最期に遺してくれたエンディングノートで検証してみました。
9箇条を実践して完成した義母のエンディングノート
義母のエンディングノートは、義母の病気が進行するに伴い、娘である相方が義母に聞き取りをすることで完成したエンディングノートです。そういう経緯があったので、相方が義母から聞き取りをする際は僕が常々言っている「もしものときに本当に役に立つエンディングノートの作り方」の9箇条を実践してもらいました。
義母のエンディングノートは僕が提案する「もしものときに本当に役に立つエンディングノートの作り方」を実践して完成した貴重な事例ということになります。
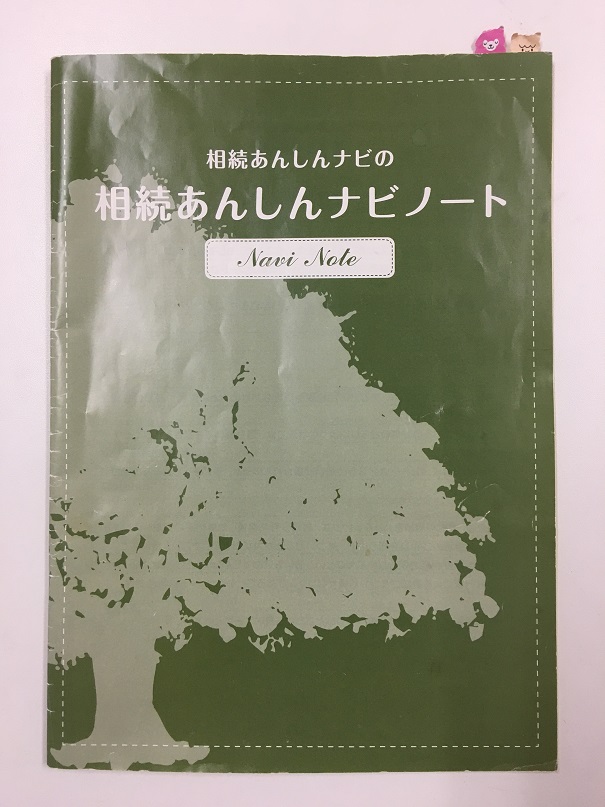
親族として葬儀やその後の手続きに関わる中で義母のエンディングノートはとても役に立っていたと思います。
関連|エンディングノートは本当に役に立つのか?|義母のエンディングノートの場合
9箇条を実践したことが、義母のエンディングノートが家族の役に立つエンディングノートになった理由だと僕は自負していますが手前味噌に感じる方もいるでしょう。
それに僕は相続人ではないので、相続人である相方に義母が遺したエンディングノートに対する率直な感想やエンディングノートについて感じていることを聞いてみたいと思いました。とはいっても内容が内容なだけに家族であっても気軽に話ができるものではありません。
また義母のエンディングノートをまるで実験台にするようで気が引けていたというのも正直なところでした。
さらに、こんな考え方は全然使えないとか、現実には無理だといった問題が白日のもとに晒される可能性もあります。でも、いつまでも机上の空論を続けていても意味がありません。
僕の活動をいつも応援してくれた義母が最期に僕に遺してくれた絶好の機会と考えて相方の協力を得て思い切って検証してみます。
義母のエンディングノートで検証してみました

義母のエンディングノートを傍に置いて葬儀や納骨、相続手続きなどを行った娘であり相続人の相方にエンディングノートを書いていたときのことや、亡くなった後のことについて率直な思いを聞いてみました。
9箇条の項目ごとに整理しています。
①書きにくいからこそ医療と介護のページから書こう
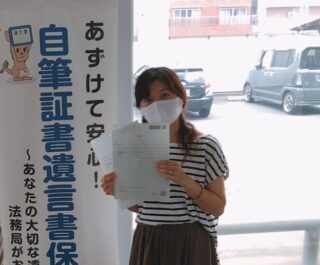
母は「医療について」のページは書いていませんでした。大事なことですがやっぱり書きにくかったのかもしれません。
もしものときになったら本人の意向を知らずに決めるのは負担が大きいので、絶対に聞いておきたかったのでちゃんと話をしました。母も家族に自分の想いを伝えておきたかったようでエンディングノートに書き留めることができました。
胃ろう(経管栄養)はしたくないと前もって聞いていたので、胃ろうをするかどうかの判断を求められたときは迷うことなく病院に伝えることができました。
絶対に聞いておきたい項目ですが、とてもデリケートな問題なので延命治療の希望など医療のページから書き始めるのは難しいかもしれません。
基本情報は家族なら知ってて当然なので書く優先順位は低いのですが、エンディングノートを書くためのウォーミングアップだと思えば基本情報から書き始めるのがいいと思います。ただし基本情報で止まってしまわないような工夫は必要だと思います。
②エンディングノートは本音で書こう
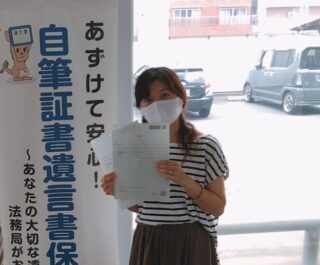
我が家の場合、母が余命宣告されてから母に聞き取りをしながらエンディングノートを仕上げたので遠慮している暇はなかったと言うのが本当のところです。お互い待ったなしで膝をつき合わせて話したので本音で話ができたと思います。
母も元気な時であれば「クリスチャンになって教会でお葬式をして欲しい」とは言えなかったと思います。母が最期の最期にクリスチャンになりたいと言い出すとは誰も想像していなかったのですが、本当に自分の最期を覚悟しての行動だったと思います。
私も「また今度聞こう」とか「また考えが変わるかも」と思うこともなく本気で聞き取りをしました。どんなお花を飾りたいか、棺には何を入れたい、、、というようなことまで具体的に話をしました。そのおかげでほとんど迷うことなく母の希望を叶えられたと思うので後悔はありません。
③必要最低限の言葉の意味を理解してから書こう
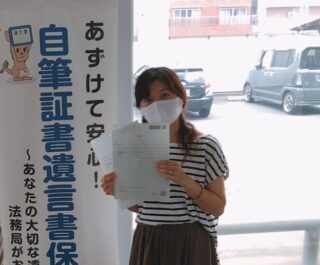
母も私も「尊厳死」の意味を十分に理解できていなかったので、尊厳死の項目は?マークを付けてそのままにしてしまっていました。医療に関する専門用語などは特に意味がわからないまま書いたところで希望が正確に伝わるとは思えません。
④正確な情報を元に書こう
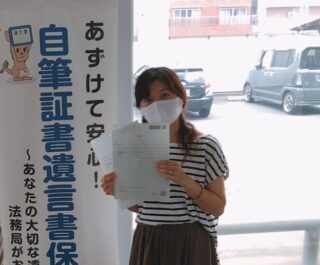
通帳や証書を見ながら母が預貯金・保険の項目は書いていてくれたので預貯金や保険の手続きはスムーズでした。
正確な内容を書いておいて欲しいのは財産に限った話ではなく健康面や病歴についても同じです。私は近くに住んでしょっちゅう会っていたので目新しい情報はありませんでしたが、もし離れて暮らしているなら病歴や服用している薬については正確に把握しておきたい情報だと思います。
⑤個人情報は書きすぎない
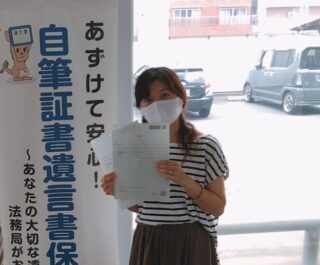
預貯金がいくらあって保険がいくらおりるということから暗証番号まで母から包み隠さず知らされていました。暗証番号はセキュリティの面からエンディングノートには書かずに口頭で聞いてきました(私にとって覚えやすいものだったのでメモの必要がありませんでした)。
そもそも母から生活費の管理等をまかされていて通帳や実印を預かっていたので隠しようもなかったと思います。
もし借金があったり保証人になっていれば、直接言えなくても相続の時に知っておきたいことなのでエンディングノートには書いておいて欲しいと思います。
⑥遺言の有無や保管場所を書いておこう
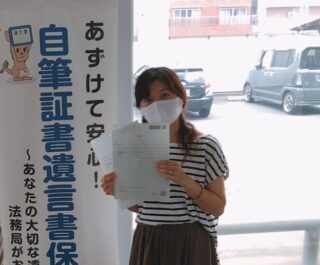
母は遺言は準備していませんでした。エンディングノート、事前に撮影していた遺影、棺に入れて欲しい写真、保険証書、実印、年金手帳などは実家の本棚にまとめていると聞いていたので必要なときに探す手間が省けてスムーズでした。
すべての情報をエンディングノートに記入しようとしなくてもエンディングノートを書きながら必要な書類を集めてまとめておくだけでもずいぶん助かります。
また、遺産については相続人(兄と私)で平等にわけるようにと口頭で伝えられていました。もし疎遠になっている相続人がいれば口頭の確認だければ法的効力もないので揉める元になるかもしれません。
これだけはと他にも3つほどお願いされたものがありましたが、いずれも口頭でそれが遺言だと受け止めています。
また、我が家の場合は基本情報や家族構成の項目は知っていることだけだったので見返すことはなかったですが、それはその家族によって違うと思います。
死後に初めて遺族がエンディングノートを見るという場合は普段面と向かって言えないことを書くことも有効だと思います。もしも私たちが知らない兄弟姉妹がいたとしたら葬儀の連絡もできませんし、相続手続きは大変な負担になったと思います。
⑦見た目や形式にこだわらない
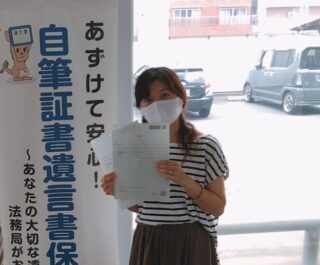
先に書いたように我が家では重要な書類はすべてエンディングノートと一緒に保管されていました。これだけでも遺族にとっては負担がずいぶん減ります。エンディングノートですべてを賄おうと気負って書き始めなくても、エンディングノートはもしものときのことを考えるきっかけの1つになるものだと思います。
⑧定期的に見直して情報の鮮度を保とう
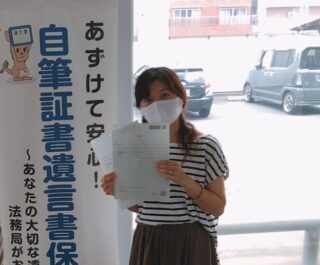
もしものときに誰に連絡するのか?は母と一緒にスマホの連絡先を見ながらグループ毎にキーマンを決めて連絡先をエンディングノートに書きだしました。ここが一番助かった項目かもしれません。スマホを見ながらだと交友関係を漏れなく把握できるのでおすすめです。
病気のことはオープンにしていたので入院するまで沢山のお友達が母のお見舞いに来てくれていました。
亡くなったときのお知らせは母のスマホから送りました。病気のことが前もって伝わっていたので滞りなくお知らせすることができました。
ただし、スマホだと電話番号はわかっても住所等はわからないことがほとんどです。下手したらフルネームがわからないということも考えられます。葬儀に来てくれた方にお礼の手紙やお香典返しを送りたいと思っても住所がわからないケースがありました。
そこは母が昔から使っていた手書きの住所録が役にたちました。もう何十年も前から使っているので何度も修正されていたりしましたが最後はこれに頼りました。
年賀状が役に立つこともあるかもしれません。エンディングノートの沢山の項目の中では、もしものときに連絡して欲しい人の情報は定期的に見直す方がいいと思います。
⑨エンディングノートを書くことはスタートです
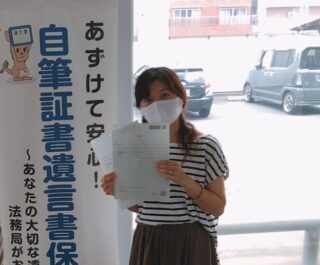
エンディングノートを書きながら使っていない口座やクレジットカードを整理したり、医療費に備えるために定期預金の解約をしました。役所の手続きがしやすいようにマイナンバーカードも作りました。
エンディングノートを書き始めたことでこれもやっておこうと次の行動のきっかけが生まれました。
母は外出するのが難しくなっていたので葬儀社の下見や契約はしませんでしたが、「私の人生が終了したら」のページを書くときに2人であれこれ相談しながら記入しました。
なにせクリスチャンのお葬式というものに参列したこともありませんし、そもそもクリスチャンのお葬式にはルールがほとんどなく、故人の遺志を尊重することを第一としていたので自由にできる反面、何を決めておくべきかはっきりわからないというのが正直なところでした。とりあえずの母の希望はこんな感じでした。
- ①〇〇教会で葬送式をしたい
- ②お墓は作らず教会の納骨堂へ納骨してほしい
- ③分骨はしない
- ④香典は辞退する
- ⑤夏(8月頭)に毎年開催される教会の慰霊祭に行って欲しい
- ⑥命日頃には納骨堂へ行ってお参りして欲しい
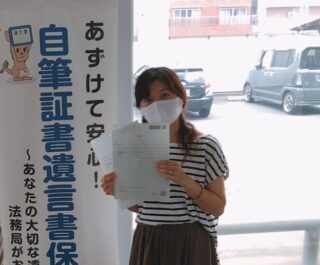
はっきりとは言われていませんが、⑤についてはお世話になった教会の牧師さんに年に1回くらいは顔を見せて欲しい、⑥は自分がいなくなることで疎遠になるかもしれない親戚との付き合いを継続して欲しいという想いがあるように感じました。
私は牧師さんとは母が亡くなった後に初めて会いましたが、母は牧師さんとも事前に相談をしていたようでエンディングノートを見ながら葬儀の準備をスムーズに進めることができました。

エンディングノートだけでは足りないところもある
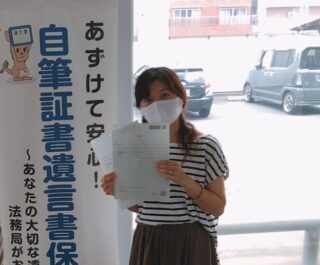
エンディングノートという言葉に引っ張られて紙媒体にこだわる必要はないと思いますが、すぐに書き込める点や持ち出しやすい点は亡くなった後の手続きをしているときに便利だと感じました。些細なメモでもエンディングノートに書くようにしていたので後でいろいろと探す手間が省けたことも良かったです。
母はSNSを利用していなかったのですがLINEとヤフーのアカウントはまだそのままになっています。SNSやネット上でアカウントを沢山持っているならパスワードの管理は紙のノートでは管理しきれないと思います。ひとり1台のご時世なのでスマホの解約やパソコンの処分も相続手続きに欠かせません。
また連絡先の整理にスマホが役に立ちました。紙のエンディングノートだけでは足りない部分もあるので他のツール等と合わせて活用するのがいいと思います。
いかがだったでしょうか?
本当に役に立つエンディングノートを作るための9箇条の視点はもしものときの家族の役に立つエンディングノートを作る上で大切なポイントを漏れなく押さえることができていると感じました。
一方で、エンディングノートを書く人が独りでエンディングノートと向き合ったとしても本当に役に立つエンディングノートを完成させることは難しそうだなとも思いました。
エンディングノート作成のサポートを必要とされる方へ
目的に適したエンディングノートが見つかればあとはご自身で書き進めていくだけですが、ひとりでは完成できるのか不安だという方もおられると思います。もしものときにご家族の負担を減らすことができるようなエンディングノート作りをサポートをいたします。
もしものときに役に立つエンディングノート作成サポート
本記事をお読みいただければ、もしもに備える目的でエンディングノートを書くときのポイントを理解していただけると思いますが、ポイントはわかったけどいざ書こうとすると書けない、どこから書いたらいいのかわからなくて書けないといったサポートを必要とされる方が対象です。
3回の個別相談(1回2時間)で伴走型でエンディングノート作りをサポートします。進捗を見てペースを上げることも可能ですが3ヶ月で完成を目指します。
エンディングノートはお持ちのものがあればそれを使うこともできますし、お持ちでなければ私の義母が使っていた「相続あんしんナビノート」を差し上げます。エンディングノートによって項目が異なるのでこちらはあくまでも一例ですが、もしものときに本当に役に立つエンディングノートを一緒に完成させましょう。
- 1回目 医療と介護、葬儀とお墓
- 2回目 家族、親族
- 3回目 資産について
依頼者ご自身のエンディングノートではなく、依頼者の方が親御さんの話を聞きながら親御さんのエンディングノートを完成させる場合にもご活用いただけると思います。
ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫

