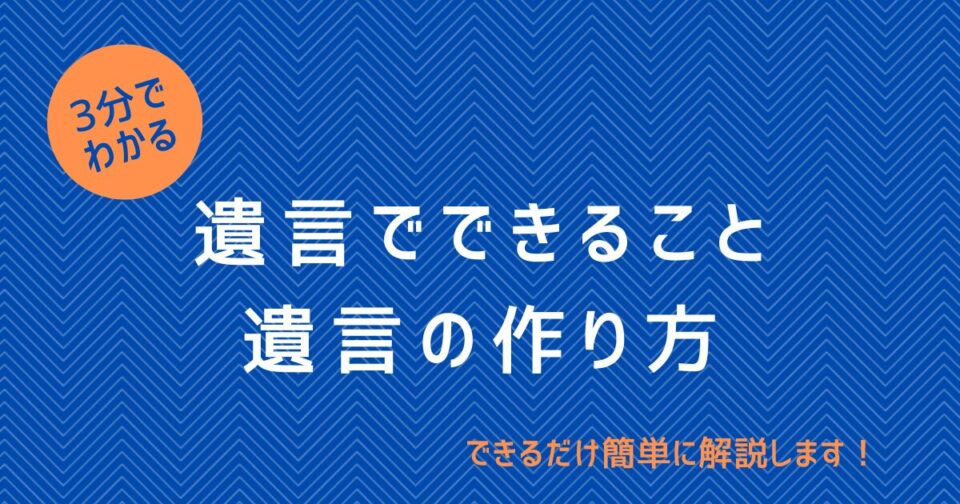
遺言に関係する記事を読んだり、まわりから相続の手続きが大変だったという話を聞いて・・・
- 遺言を書いておいた方がいいのかな?
- 書いておきたいけど書き方がよくわからないなぁ
- エンディングノートに書いておけばいいの? etc.
どうしたらいいんだろう?と迷ってしまっている方も多いと思います。
目次
遺言とは?

遺言が気になっているけどわからないことだらけで不安を感じている方に向けて、相続専門の司法書士・行政書士がまとめた記事です。わかりやすさを優先してできるだけ専門用語を使わずに書いています。

遺言はウィキペディアではこのように説明されています。読み方は「ゆいごん」でも「いごん」でも好きに読んでいただいてOKです。
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。
ウィキペディア
日本公証人連合会の公式サイトに書かれていた遺言の意義が遺言の本質をわかりやすく表していると感じたのでご紹介します。
遺言の意義
日本公証人連合会の公式サイト
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です
遺言でできること
民法で決められたルールに従えば遺言に書く内容は自由です。ただし、法的な効力を持つのは「法律で規定された事項」に限られます。遺言は遺言を書く人の一方的な意思なので、できることは以下のように限定されています。
- 相続分の指定や遺産分割方法の指定など相続に関すること
- 遺言執行者の指定や祭祀承継者(先祖の供養やお墓を守る人)の指定など
- 遺贈や信託の設定など財産の処分に関すること
- 認知・未成年後見人の指定など身分に関すること
※未成年後見人を指定するには、遺言の形式によらなければなりません。

子供がいないので、全財産を妻に相続させたいです。

遺言で法定相続分と異なる割合で遺産の分配ができます。次のような希望を叶えることができます。
・老後の面倒をみてくれる子供に多めに相続させたい
・家族に迷惑をかけてきた子供には相続分を少なくしたい

相続人どうしが疎遠なので争いが生じないか心配です。

遺言で遺産の具体的な分配方法を決めることができます。
長男には自宅を長女には現金をというように遺産の具体的な分け方を決めておいて、遺産分割協議の苦労を軽減させることができます。
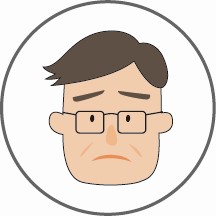
面倒をみてくれている息子の嫁にも遺産をあげたいです。

遺言で法定相続人以外の方に財産をあげることができます。次のような希望を叶えることができます。
・相続人がいないので、お世話になった方に遺産をあげたい
遺言のよくある質問
何度でも内容の取り消し、変更をすることができます
確実に遺言の内容を実現するために、信頼できる人を遺言執行者に指定することができます
生前だけでなく、遺言でも認知をすることができます
法律上の効力はありませんが「付言事項」として記載することができます
遺言とエンディングノートの違い
エンディングノートとは、自分の経歴や思い出、もしものときに連絡して欲しい友人の連絡先、葬儀や墓の希望、尊厳死や延命治療に関する自分の考えなどをまとめておくノートのことです。
エンディングノートの中には相続や遺産分けに関するページがあるものもあるので、勘違いをしている方も多いのですが、エンディングノートには遺言のような法律上の効力はありません。
エンディングノートは、遺言に盛り込めない想いや情報をご家族や身近な方に伝えることに役立てることができます。
関連|もしものときに本当に役に立つエンディングノートの作り方
遺言の種類
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つが一般的です。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
まずは、それぞれの長所・短所を把握しましょう。続いて2つの遺言の作成方法を説明します。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどっちがいいの? 【2つの遺言の長所と短所】
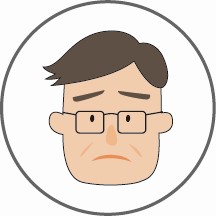
【Aさん】
費用はあまりかけれないし、手書きも面倒くさい・・・
そんな私が作るなら自筆証書遺言と公正証書遺言のどっちがいいと思いますか?

自筆証書遺言と公正証書遺言はそれぞれ長所、短所があります。
自筆証書遺言には法務局に預ける自筆証書遺言書保管制度もあります。この制度を利用する場合は自筆証書遺言の短所が解消されるので、順を追ってみていきましょう。
自筆証書遺言
【長所】
- 自分ひとりで作れる
- 誰にも知られずに作成できるため、遺言の内容や存在を秘密にできる
- 費用がかからない 1)
【短所】
- 形式の不備等により無効になるおそれがある 1)
- 相続人に発見されないことがある 1)
- 改ざんのおそれがある 1)
- 裁判所の検認が必要 1)
1)自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、手数料(3,900円)がかかりますが、自筆証書遺言の短所を解消することができます
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合

自筆証書遺言を法務局に預ける自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、自筆証書遺言の短所を解消することができます。
ただし、遺言の内容は審査の対象外なので、遺言の内容があいまい・不正確な場合にトラブルになってしまっても自己責任です。
自筆証書遺言は仏壇や金庫で保管されることが多く、なくしたり書いたことを忘れてしまったり、また相続人によって隠されたり改ざんされたりと、自筆証書遺言が適切に保管されていなかったことで相続トラブルが起きてしまうという課題がありました。
こういった課題に対応するために自筆証書遺言を法務局で保管する制度が2020年7月10日からスタートしています。
日付の記載や押印の漏れなど、形式に不備がないかどうかの確認をした上で、問題のない自筆証書遺言が保管されます。
また、本制度を利用して法務局に自筆証書遺言を預けている場合は、遺言が保管されているかどうかの確認をすることができます。
自筆証書遺言書保管制度を実際に利用して感じた率直な感想をまとめました。利用を検討している方は参考にしてみてください。
関連|夫婦で遺言を書いて法務局に預けてみた|自筆証書遺言書保管制度の利用レポート
自筆証書遺言の保管場所による違い
- 自筆証書遺言書保管制度を利用することで裁判所の検認が不要になります
- 保管制度を利用するには手数料がかかります
- 保管制度を利用するには遺言者本人が法務局に行く必要があります
| 自宅等で保管 | 法務局で保管 | |
| 裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
| 手数料 | 不要 | 3,900円 |
| 本人確認 | 不要 | 遺言者本人が 法務局に出頭 |
| 確認方法 | なし | あり |
自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に自筆証書遺言を預けている場合は、遺言が保管されているかどうかの確認をすることができます。
※公正証書遺言の場合、平成元年以降のものについては日本公証人連合会の遺言情報管理システムを利用して、検索することが可能です
公正証書遺言
【長所】
- 公証人が関与して作成するため、信頼性が高い
- 公証役場で保管 1)されるため、改ざんのおそれが低い
【短所】
- 2人以上の証人が必要 2)
- 内容を秘密にできない
- 費用がかかる
1)東日本大震災は未曾有の大震災だったにも関わらず公証役場で保管されていた公正証書遺言の原本は破損・紛失が1つもなかったそうです(参考「東洋経済 8/6号」)。この事実を知って驚くとともに、公正証書遺言をおすすめしようと思う理由になりました。
2)受遺者(遺言によって遺産を譲り受ける者)及びその配偶者、推定相続人等は証人になれません
※自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所は大分地方法務局の公式サイトを参考に作成しました。
公正証書遺言だけができること
公正証書遺言は、体力が弱り、あるいは病気等を理由に、遺言を手書きすることが困難になった場合でも公証人に依頼することによって、遺言を作成することができます。
まとめ
自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらが良いかは、手軽さ・費用面、トラブルにならず確実に遺言を実現したい等を判断基準に選択することが一般的です。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言の短所を解消することができます。 状況の変化に応じて何度か作り直す可能性があるなら、先ずは自筆証書遺言、最終的に公正証書遺言という方法も考えられます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法
自筆証書遺言の作成方法
- 遺言者が日付、氏名、財産の分割内容等を手書き 1)し、押印をして作成する。
1)財産目録については、パソコンで作ったり不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを別に添付する方法も認められています(2019年1月13日から)
公正証書遺言の作成方法
- 遺言者が、2人以上の証人とともに公証役場 2)に出向き 3)、遺言の内容を公証人に口授し 4)、公証人が遺言を作成する。
2)「公証役場」とは、公証人が執務をするところで、全国に約300ケ所あります。公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証等の業務を行っています
3)遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合は、自宅等へ公証人に出張してもらうことも可能です
4)病気等のために自筆証書遺言が書けない方でも遺言を作成することができます
遺言者の自書が不要
日本公証人連合会の公式サイト
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。他方、このような場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
Q. 検認をすると有効な遺言だと認められますか?

自宅などで保管している自筆証書遺言は、手続きをする前に家庭裁判所で検認をする必要があります。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認をすることで、遺言の有効・無効が判断されるわけではありません。

【Aさん】
「遺言を書いているから後はA君頼むね」と叔母から言われていて、叔母の遺言を預かっています。
調べてみたら検認という手続きが必要になるみたいですね。検認をすることで、叔母の遺言が有効な遺言だと認められるのですか?

検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認手続きで遺言の有効・無効が判断されるわけではありません。
検認申立ての必要書類
必要となる主な書類です。
- 検認申立書
- 遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
親、兄弟姉妹が相続になる場合は、上記以外にも戸籍謄本を集める必要があります。

【Aさん】
そうなんですね。叔母の遺言は私に全財産を譲るという内容です。それでも相続人全員の戸籍が要るんですね。
相続人は私を含めて10人以上いるので戸籍を集めるだけでも大変そうです。

自筆証書遺言の発見者や保管者が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりしないように、家庭裁判所に相続人が集まって遺言の存在を明確にして、偽造・変造などを防止することが検認の目的なので、相続人全員の戸籍が必要になります。
検認の申し立てをした人は、指定された日時に家庭裁判所に行かなければいけませんが、申立人以外の相続人は出席してもしなくてもかまいません。
また、遺言書に封がしてある場合は、家庭裁判所で開封する必要があります。検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
ちなみに、自筆証書遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言を法務局に預けると検認は不要になります。
ただし、遺言書情報証明書の交付請求のときに、相続人全員の戸籍が必要になるので戸籍を集める手間は変わりません。
Q. 遺言を貸金庫で保管しています。大丈夫でしょうか?

自筆証書遺言を貸金庫に保管することは、おすすめできません。
貸金庫の相続手続きをしなければ貸金庫が開扉できないので、遺言の内容の確認に時間と手間がかかってしまいます。
相続人が遺言の存在を知らなければ、遺言が相続人に発見されないままに遺産分割が進み、それが相続人間のトラブルに発展するおそれもあるからです。

【Aさん】
遺言(自筆証書遺言)をなくさないように銀行の貸金庫で保管しています。貸金庫で保管しているのは、遺言を書いていることや内容を家族に知られたくないことも理由です。
某銀行の貸金庫の事件を知って、なんだか心配になってきました。

自筆証書遺言を貸金庫で保管することは2つのリスクがあります。
遺言の内容の確認に時間と手間がかかることが、1つ目のリスクです。
貸金庫の中の遺言を確認するには、貸金庫を開扉するのにいわゆる相続手続きが必要になります。
貸金庫の手続きをするには、その支店に行かなくてはならず、遠方の場合は遺産分割が遅れる原因になります。
貸金庫を利用している方は、おそらく相続税の申告が必要な方が多いでしょう。
相続税には申告期限があるので、相続開始後早い段階で相続の方向性を決めなければなりませんが、相続人は遺言が見つかるまでは相続の方向性を協議することができません。
もう1つのリスクは、自筆証書遺言が相続人に発見されないまま遺産分割が進むリスクです。
相続人が遺言及び貸金庫の存在を知らなかった場合は、相続手続きを進める中で貸金庫を借りている金融機関で手続きを開始して初めて遺言があることを知ることになります。
あらかじめ、相続人の遺産分割協議で決めた内容と、発見された遺言の内容が大きく異なれば、相続人間のトラブルに発展するおそれがあります。
誰にも知られずに自筆証書遺言を保管したいということなら、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討することが考えられます。
この制度を利用すると自筆証書遺言の原本は法務局に預けるので、Aさん(遺言者)の手元に残るのは保管証だけになります。
亡くなった後に通知可能 【指定者通知】
自筆証書遺言書保管制度には、指定者通知という仕組みがあります。
遺言書保管官が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめAさん(遺言者)が指定した方に対して遺言書が保管されていることをお知らせするものです。
この方法で、亡くなった後で遺言の存在を確実に知らせることができます。
Q. 秘密証書遺言はどんな遺言?-秘密証書遺言の特徴と注意点について-

【Aさん】
遺言のことを調べていて、秘密証書遺言という遺言を知りました。
遺言を作ったことは家族に内緒にしておきたいのですが、秘密証書遺言は、どんな遺言なんですか?

秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたい場合に利用される遺言で、遺言を封印して公証人と証人の前で確認を受けます。
秘密証書遺言は自筆でなくても作成できることが特徴です。また、公正証書遺言と違い、亡くなった後に検認手続きが必要になります。
秘密証書遺言の特徴
☑ 遺言の内容を秘密にできる
- 自分で用意した遺言を封をした状態で公証役場に持っていくため、遺言の内容が他人に知られることはありません
☑ 自筆でなくても良い
- 自書しなくても、他人に書いてもらっても、プリントしたものでもかまいません
秘密証書遺言の注意点
☑ 保管上の課題
- 公正証書遺言とは異なり、遺言が公証役場に保管されないので、紛失や改ざんなどへの対策が必要になります
☑ 検認が必要
- 亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きが必要になります
証人の立会いの元、公証役場で作成 ※)するのは公正証書遺言と同じですが、公証役場に残るのは遺言を作成したという事実のみで、遺言の内容までは記録保管されません。
そのため、遺言を紛失してしまうおそれもあります。
また、秘密証書遺言は、公証人は遺言の存在のみを確認するだけで遺言の内容そのものを確認しないため、自分ひとりで作った遺言がはたして法律的に有効なものなのか?亡くなるまでわかりません。
そもそも「秘密」という点に着目するなら、自筆証書遺言であれば自分ひとりで誰にも知られずに作れるわけで、秘密にしたいという部分だけで考えれば自筆証書遺言に軍配が上ります。
※作成という部分を補足します。秘密証書遺言は、民法で次のように定められています。
(秘密証書遺言)
民法
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
三号の封書というのは封筒のことです。事前に作成した遺言を封筒に入れて状態で公証役場に持参します。
四号の封紙も封筒のことです。封紙に記載するのはまれで、通常は、公証人が用意した用紙に所定の事項等を記載し、これを封筒に貼付するようです。
秘密証書遺言が利用される場面
ちなみに、秘密証書遺言がどの程度、利用されているのかというと、年間100件前後のようです。利用されるのは、非常に稀なケースだろうと想像ができます。
秘密証書遺言が利用される場面として、「月報司法書士 No.593」に次の5つが紹介されていました。
① 財産目録のみならず、本文も自書でなくパソコン等で印字したい場合
出典:「秘密証書遺言の活用場面」 月報司法書士 No.593
② 口授ができない遺言者が遺言をする場合
③ 偽造、改ざんを防止できること
④ 手数料を安価に抑えられること
⑤ 遺言書作成の動画等を残すために利用すること
① は秘密証書遺言は自書である必要がないので、司法書士や弁護士など専門家に作ってもらっても問題がないので、秘密証書遺言を選択する理由になるかもしれませんが、そうなると秘密にできることを重視しているとは思えません。
② 口授は「くじゅ」と読みます。「口伝えに告げて教えること」という意味です。
公正証書遺言は、遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないとされていますが、発語が不自由な遺言者については、通訳人の通訳による申述で口授に替えることができるので、秘密証書遺言を選択する理由としては弱いかもしれません。
③ 公正証書遺言も偽造、改ざんを防止できるので、秘密証書遺言を選択する理由としては弱いかもしれません。
④ 秘密証書遺言の公証人手数料は一律11,000円です。
公正証書遺言の公証人手数料は、遺言に記載する財産の価格や相続させる人数によって変わります。財産の価格が大きいと公証人手数料も高額になるので、費用面から秘密証書遺言を選ぶことはあると思います。
⑤ 秘密証書遺言は封印した封筒の中に遺言書以外の物を入れることが可能なので、遺言者が遺言を作成した理由や動機を話している様子を撮影して、それを保存したDVDなどを封筒に入れておくという使い方ができるということのようです。
手紙に残すよりもわかりやすいと思いますが、同じ封筒に入れておけることが秘密証書遺言を選択する理由と言われると、本当にそうだろうか?と思ってしまいます。
また、保管上の課題、検認が必要になること以外の秘密証書遺言の問題点(注意すべき点)も紹介されていました。
- 自署ができない遺言者は、作成できないこと(自署するのは遺言ではなく封紙です)
- 封印に用いる印鑑が遺言書に押印した印鑑と異なると、秘密証書遺言として効力がないこと
- 公正証書遺言の場合は公証人が遺言者の遺言能力の有無について確認し、法律的に問題のない内容の遺言であることを確認した上で遺言書を作成するが、秘密証書遺言では公証人がこれらをチェックすることは不可能であること
この記事を書かれた公証人の先生も秘密証書遺言は1件しか経験がないそうです。まわりの公証人に聞いても秘密証書遺言を作成した公証人は皆無だったそうです。
どうしても秘密証書遺言で遺言を作成したいという理由や場面が思いつかないのですが、もし、こんな事情があるから秘密証書遺言を作りたい、こんな理由で作成しましたという方がいらっしゃいましたら、後学のためにお話を聞かせていただければ幸いです。
ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫

