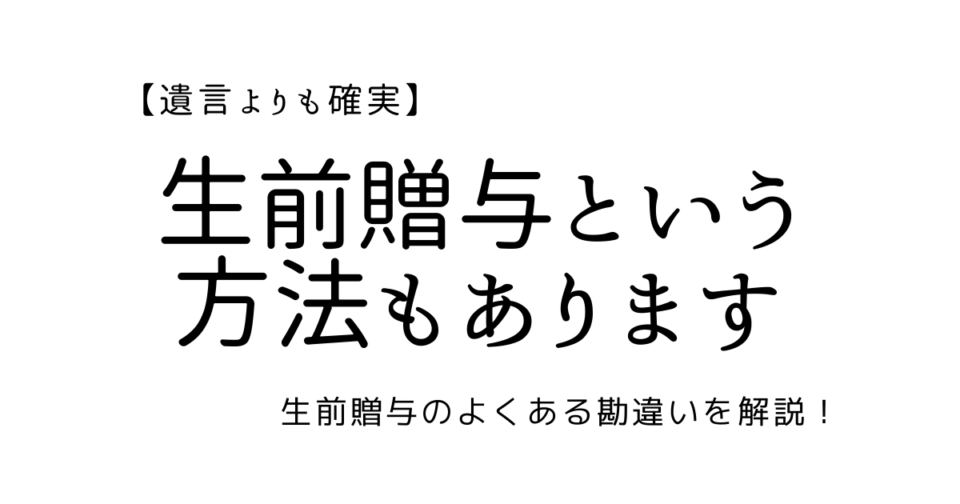

財産の渡し方には遺言の他に自分が元気なうちに渡しておく生前贈与という方法があります。自分で財産を渡すことができるので確実ですが、渡し方や費用・税金について勘違いをしている方が多いようです。
みなさんは大丈夫ですか?
目次
遺言と生前贈与の違い
遺言で財産を渡すことができるのは自分が亡くなったときです。
それに対して生前贈与は自分で直接財産を渡すことができるので、やはり確実なのは生前贈与です。
生前に贈与することで、亡くなった時の相続税の負担を減らすことにつながります。ただし、相続税ではなく贈与税の対象になるので相続時精算課税制度などを利用しなければ税金が高くなる場合もあります。
一方で、生前に必要以上に財産を渡してしまうと、自分自身の将来の生活に不安を覚えるという本末転倒の事態になってしまう恐れもあります。
遺言を書こうか迷ったときには、この辺りのバランス感覚を持ちながら、遺言だけでなく生前贈与についてもあわせて検討することをおすすめします。
生前贈与のよくある勘違い
将来の相続税を心配されて、元気なうちに自宅などの不動産を子供や孫の名義にしておきたいといったご相談を受けることがあります。いわゆる生前贈与ですが、生前贈与のよくある勘違いについてご紹介します。
あげたい人が勝手にはできません
私があげたいのだからもらう人の意思なんて不要では?と思っている人がいますが、生前贈与は【契約】ですから「あげる人」と「もらう人」の合意が必要になります。
売買ではないので、こういった勘違いをしている方が結構いますが、もらう方も欲しくないものを押しつけられるのは困りますよね。また、後日合意を証明できるように贈与契約書をしっかり作っておく必要があります。
不動産の場合|名義変更に伴う費用をお忘れなく

【よくある勘違い】
基礎控除額内で数回に分けて名義変更をすれば、贈与税がかからなくてお得なのでは?
毎年110万円の基礎控除額内に収まるよう複数回に分けて贈与すれば贈与税はかからないかもしれませんが、分けて贈与した分だけ、登記費用(司法書士の報酬)×登記の回数分が余分にかかります。※自分で登記申請をする場合は当てはまりません
そこで複数回に分けてするのと、贈与税を払ってでも一度でするのとでは、全体の費用はどちらが安くなるのかという視点が重要になります。
不動産の価格は110万円を超えることが多いので、非課税枠内で贈与するために不動産の持ち分を贈与するケースが多いでしょう。その場合は現金と異なり110万円以下になるよう贈与する持分を決める必要があります。
一度決めても地価の変動があれば110万円を超えないように持分を見直すことや、教育資金や結婚・子育て資金といった贈与税の非課税制度の動向を確認するなどして、前年と同じ内容で贈与することがベストなのかを毎年検討した方がよいでしょう。
ちなみに僕(司法書士・行政書士)は地価や税金については専門外なので、こういったケースでは税理士さん、不動産鑑定士さんなどの各分野の専門家と一緒に対応するようにしています。
また贈与税を気にされる方はとても多いのですが、不動産を贈与すればこういった費用も掛かります。
- ①不動産取得税
- ②名義変更(登記)の登録免許税
- ③固定資産税・都市計画税
①例えば1,000万円(評価額)の土地(宅地)を贈与した場合の不動産取得税は15万円になります※減額の適用はないと仮定して試算
②同じく1,000万円(評価額)の土地(宅地)の場合は、20万円の登録免許税が必要になります。※令和4年2月時点
いますぐにでも贈与したいというご相談だったのに、この負担に気がついた途端にやっぱりやめておきますとおっしゃる方は多いです(苦笑)。
現金の場合|同じ1,000万円でも結果は大違い
不動産だけでなく、現金についても贈与税の非課税枠110万円を活用して贈与税がかからないように、何度も贈与することを検討されている方は多いです。

【よくある勘違い】
毎年、贈与契約書を作るのが面倒だからまとめて10年分を作ってしまおう
これは、年100万円の現金×10年間の合計で1,000万円を贈与するようなケースです。中には、毎年、贈与契約書を作るのも面倒だからまとめて10年分を作ってしまおう。そうしておけば後はお金を毎年渡すだけでいい。これで完璧だ!なんて満足されている方もいるのかもしれません。
これは1,000万円の贈与で単にお金の渡し方を10回(10年)に分けただけと税務署に判断される可能性があるようです。
一年間に100万円を贈与することには税金がかかりません。これを10年間同じように行った結果として1,000万円を贈与することには贈与税がかからないということなので、1,000万円を10回に分けて渡すこととは全く意味が違うというのが税務署の考え方というわけです。

そこで毎年100万円のように毎年同じ金額にせず、あえて120万円や140万円などの110万円を超えた金額を贈与して都度、贈与税を納めておくことが毎年贈与しているひとつの証拠になるということを税理士さんに教えてもらったことがあります。
なんだか面倒だなと感じるかもしれませんが、不動産に比べれば現金は比較的シンプルでわかりやすいです。
贈与税がかからないことがベストなのか?
贈与する人が亡くなってしまえば生前贈与はその時点で終わりです。もし贈与していたのが自宅の土地の持ち分であれば、他の相続人と自宅の土地を共有することになる可能性があります。
財産を受け取って欲しい人が確実に単独で所有できることを優先して、贈与税を納付してでも一括して贈与しておく方が後々不要なトラブルを発生させないで済むという考え方もあります。
贈与税がかからないから。
これだけを基準に判断することがベストなのか?は一度考えていただきたいと思います。現金は生前贈与で、自宅など不動産は遺言に書いておくというように遺言と生前贈与を組み合わせる方法もあります。
高齢の配偶者に対する居住用不動産の贈与などを保護する制度
自宅を生前に配偶者に贈与したとしても原則は遺産の先渡し(特別受益)があったと考えるので、結果的に配偶者が受け取れる財産の総額は贈与があろうがなかろうが変わりませんでした。
配偶者を想って贈与しているのに、その意思が反映されないことが課題になっていました。
新制度の概要
結婚して20年以上になるご夫婦で生前贈与や遺言で配偶者が自宅を受け取った場合、自宅は遺産分割の対象から除かれることになります。
新制度では自宅について遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなります。なんだか専門的でわかりにくいですよね。
こちらの事例を元に考えてみます。参考「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について」法務省のサイト
配偶者が最終的に受け取れるのは・・・
- 現行制度では・・・5,000万円
- 新制度では・・・・・6,000万円
新制度では1,000万円多くなります。違いは遺産総額の計算をするときに生前に贈与を受けていた居住用不動産(1/2の持分)を加入しないからです。
亡くなった人から特定の相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合に、相続人間の公平を図るために具体的な相続分を修正するのが特別受益の考え方です。ただし、特別受益となるのは婚姻・養子縁組のため、生計の資本としての贈与のみが対象になります。
配偶者に自宅の持分を贈与したことは、特別受益となり原則は遺産総額の計算に含める必要がありましたが、今回の改正でその必要がなくなったということです。
ただし、配偶者が優遇されるといっても、贈与や遺贈してもらわないと優遇されないので日頃から大事にしておかないとという話しですよね。
時代にフィットする改正かもしれません
離婚・再婚が増えていることに伴い、相続人が配偶者と子供というケースで、配偶者と子供が血縁関係のないケースが増えていることが想像できます。
親に住所を知られたくない。実の親と縁を切る方法はありませんか?
両親の離婚で小さい頃からずっと離れて暮らしてきた。だから実の親かもしれないけど今の生活を壊したくない。
実の親との関係を終わらせたいという方や、亡くなった後でも関りを持ちたくないと相続放棄をされた方もいました。
血のつながりがない親の再婚相手と連れ子が仲の良いケースも知っているので、血のつながりがすべてとも思いません。
とはいえ、相続人同士が血縁関係のないケースが増えてくれば、高齢の配偶者の生活が保障されることにつながる今回の改正は時代にフィットするものだろうと感じています。
迷ったときは複数の専門家に相談しよう
専門家といっても全ての分野に精通しているわけではありませんし、何年も先のことを見通せるわけでもありません。だから10年20年先を見据えた贈与計画を練り上げたとしても果たしてそれがベストなのかどうかは誰にもわかりません。
少なくとも自分ひとりの思い込みだけで判断したり、一人の専門家の話を鵜呑みにするようなことはせずに、各分野の専門家の意見を聞いてみることがベターな解決策が見つかる可能性が高いでしょう。
司法書士・税理士・弁護士などの各分野の専門家が一同に会する相談会を定期的に開催していますので、ぜひご活用ください。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫

